Your Site Title / Tamplate#019
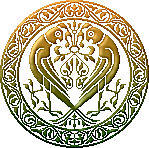
『既成事実、寵愛の一夜』【5】
シーアは、リリアン・ウェイの言葉に耳を傾けていた為、皇太子宮殿から注がれる視線に全く気付く事なく、洋紙(→略図←)に視線を落としていた。
「13の側室称号が存在すると同時に、皇太子殿下の宮には同称号のお部屋が設けられております。称号を与えられると、そのお部屋は側室さまが皇太子殿下を迎える大切なお部屋となるワケです」
シーアは頷いた。
そうすると、わたしは “緑晶の間” を与えられたって事になるのよね?
でも、それがどうしてアリーシャさまから憎まれる事になるの?
リリアン・ウェイは、三角形に位置している3つの称号を指した。
「この緑晶・緋晶・蒼晶は、宮廷における大貴族・大臣たちの姫がその座を与えられ、領主の姫や忠臣たちの姫・外国から嫁がれた姫がその下位の紅晶から蒼金晶・菫晶・碧晶を与えられました。身分は低いけれど、とても美しく皇太子の目に留まった女性は、独立した淡晶・白晶を与えられたのです」
リリアン・ウェイは、側室称号を指しながら再び話し始めた。
「現在、皇太子殿下のハーレムに、側室は緋側・アリーシャさまを筆頭に、紅側・黄側・蒼金側、そして白側さまの5名しかおられません。ローレルさまが戴いた緑側を除くと、側室の空席は7つです。その他の女性は、皇太子殿下・ホークさまから未だ側室称号を授かってはいないのです。……つまり一夜の伽ぐらいでは、殿下のお心を捕える事は出来ないのです」
シーアは、リリアン・ウェイの説明に納得がいかなくて口を挟んだ。
「でも、わたしは……この国の民でもなければ、大臣たちの姫でもない。しかも、たった一夜宮に出向いただけなのに……それなのに、どうしてわたしは “緑晶の間”
を与えられる事になったの?」
リリアン・ウェイは、シーアの秘密を探り出そうというように、エメラルド色の瞳を真摯に見つめた。
そこで、フッと表情を緩めると、シーアを憧れの眼差しで見上げてきた。
「 それは……きっとローレルさまの中にある……ナニカが皇太子殿下・ホークさまの琴線に触れたんだと思います」
「まさかっ! 彼は、わたしを物のように扱ったのよ。その辺に居る女と同じように!」
シーアは、荒立たし気に息を吐き出した。
最初の出会いからして、シュザック皇子は……わたしを物のように大金で買い、そして皆の前でキスを……。
あの時のキスが突然思い出され、シーアは知らず知らず柔らかい唇に触れていた。
あんな奪うようなキスをしたけれど、結果わたしは娼館に買われる事はなかった。本来なら、今頃いろんな男の腕の中に居たハズだ。
ゾクッと寒気が背筋に走り、シーアは我が身を守るように両手で躰を強く抱き締めた。
「それでも、ローレルさまは幸せですわ。ハーレムに連れてこられたとしても、 “緑晶” の地位を……すなわち翡翠の位・ジェイダイトの称号を手に入れたのも同然なのですから」
「その “緑晶” とはいったい何なの?」
シーアの悲痛な問いかけに、リリアン・ウェイはゆっくり話し出した。
「先程申し上げたハーレムの側室称号ですが、それは先代王の時代までです。皇太子殿下・ホークさまの父君、現ガリオン帝国王が皇太子だった頃の話ですが、その時漆黒の髪に漆黒の瞳・白い肌を持つ美しい女性が、ガリオン帝国に現れました。その女性の出身地は明らかにされてませんが、街で大層評判になり当時皇太子だった現王がお忍びでその女性を見に行ったらしいのです。一目で恋に落ちた現王は、彼女をハーレムへ連れて帰り、緋側や蒼側よりもその女性を毎日宮へ呼び寄せ、いつしかハーレムへ戻る事も許さなくなったのです」
「まぁ!」
それほどまでに魅力ある女性だったの?
シーアはより一層身を乗り出して、リリアン・ウェイの話に聞き入った。
* * * * *
「殿下、ここは一つハーレムに “戒めの命” をお出しになっては?」
ギルは、庭園での様子を殿下や殿下直属の部下でもある……アルマン伯たちと共に眺めていたが、あまりにもローレルへの風当たりが強い為、思わず進言したのだ。
ローレルの事を知っているアルマンも、同意するように頷いたが、殿下は手すりに凭れてただハーレム内の出来事を眺めていた。
「そうする必要もないだろう。俺が、今夜アリーシャを呼べばいいのだから」
「はぁ……」
ギルは、それでいいものかどうかわからなかった。
皇太子のハーレムには、権力者たちの姫や殿下のお眼鏡に叶った女が居て、どの女もそれぞれ魅力的だった。
だが、ローレルがその女性たちから仕打ちを受けているのを観ると、どうしても心が騒いでしまう。
一緒に長旅をしてきた間柄だからか? それとも、あの道中……不意に躰が反応したからだろうか?
確かに、ローレルには普通とは違った感情を抱いている。それが良い事にしろ、悪い事にしろ。
ギルは、横目で殿下を見つめた。
殿下の顔には、何も浮かんでいない。喜怒哀楽のどれも……。
だが、その瞳は左右に動かず、ただ一人の女性だけを観ているようだった。
ギルは、再び庭園を眺めた。
殿下がハーレムを覗いてる事を知った姫たちは、寵を戴こうと蝶のようにひらひらと動いて美しさを披露していた。
ただ一人……ローレルだけは侍女と何やら話し込み、周囲に視線を向ける事なく侍女の話に聞き入っている。
彼女だけが、殿下からの寵愛を欲しがろうとしていなかった。
ギルは、再度殿下を盗み見した。
先程と寸分違わず、同じ場所ばかり眺めている。
だが、その表情には明らかに違った面があった。
口元は微かに綻び、漆黒の瞳には何やら決意に満ちた光が宿っている。
「……殿下?」
「ギル、ハーレムへ行くぞ」
「えっ?」
いつもならハーレムへ直接行くような事はしない為、ギルは驚愕を隠せないまま殿下を見た。
「俺の口から、今夜の為に支度をするよう告げる事にした」
まるで、今から楽しい事が起こるとでもいうように、唇の端を上げるとニヤッと笑った。
マントを翻して進む殿下を、ギルは追った。
その後を従うように、アルマンたちも歩を進めた。
「これが終わったら、騎馬養成所へ出向き、兵たちの士気を高める事にしょう」
「はい」
ギルは、後ろに続くアルマンたちと目くばせをすると、殿下に遅れないよう付き従った。
* * * * *
「……現王は、その女性に称号を与えたかった。でも、緋側や蒼側の下位になるのは許せなかったのです。そこで、現王は先代王に直談判し、ハーレム内の改訂をするべく実行に移しました」
シーアは、洋紙に視線を落とた。
今の現王は、地位の低い女性を側室にしたかった。でも緋側や蒼側の下位になる地位を授けるつもりはなかった。緋側たちと同等の地位、もしくはそれ以上の地位を……与えたかった?
シーアは急に不安を覚えた。何故なら、今話してくれた中で……ぽっかりと緑晶の地位・緑側だけが空いていたからだ。
もしかして……?!
「同等の地位だった緋晶・蒼晶・緑晶でしたが、現王は緑晶を一つ上の位に上げ、ハーレムの中でのトップの地位を作られたのです。本来、側室は正妃を助ける役目もありましが、現王は緑晶の称号を持つその女性に、翡翠の位・ジェイダイトまで授けました。ジェイダイトとは、独立した女性を意味し……正妃と同等の身分に相当するのです」
シーアは、その内容に頭がクラクラしてきた。
口に出すのもおぞましい程だ。
「ジェイダイトの地位を得たその女性は、正妃よりも早くにご懐妊され男児を出産なさいました。当然の事ながら、先代王の初孫にあたる男児が、後継者に決定しました。もちろん大臣クラスから反対の声が上がりましたが……それをも覆すジェイダイトの地位が物を言い、結局はジェイダイトの長男が皇太子になられました」
「皇太子……?」
「はい。そうです」
ま、まさか……その皇太子って、
「シュザック皇子の事なの?!」
「はい。今では、皇太子殿下の知性や判断力・統治性が非常に優れている為、この事を公に公言し問題視する大臣などは……誰もおりませんが、皇太子殿下は母君の苦労を知っておられたので、あえて緑晶の地位を空白にされているのだと囁かれておりました」
「なら、どうしてわたしを?! 馬鹿げてる……、そんなにいろいろあったと知っているのに、どうしてわたしを “緑晶の間” へ通したりしたの?」
リリアン・ウェイは、手元の洋紙を畳むと胸に忍ばせた。
「ジェイダイトさまは、漆黒の髪に白い肌を持つ……とても綺麗な女性だったと伺っております。ジュダイトさまの白い胸元に光る、大きなエメラルドが……ローレルさまの瞳と似ていて、皇太子殿下の記憶に残る微かな破片に触れたのかも知れませんわ。それに境遇も……」
リリアン・ウェイが漏らした最後の言葉は、シーアの耳に届かなかった。
それほど、鬱積した怒りが躰中から溢れそうだったのだ。
「勝手に感傷に浸らないで欲しいわ! 結局は、シュザック皇子が気まぐれでわたしを “緑晶の間” へ通したりしなければ、こんな事にはなかったのに」
シーアは、身振りでハーレムを指した。
シュザック皇子は、何て事をしてくれたの!
だが、ふとシーアは我に返った。
大丈夫よ……そうよ、大丈夫だわ! わたしは、明日ココから逃げ出すのだから。そうすれば、ハーレムの事情など余計な事は一切関係なくなる。
そう思うと、フッと心が軽くなった。
その時、庭園がにわかに騒がしくなった。
周囲を見渡せば、ハーレムの女性は回廊へ集まって膝を折っていた。
「何? どういう事?」
「ローレルさま! わたくしたちも行かなければ!」
「どうして?」
手を引っ張られて長椅子から立ち上がった時、漆黒の髪に漆黒のマントを着たシュザックが現れた。
彼は、侍女と共に佇むシーアに、射るような眼差しを向けていた。
漆黒の髪に漆黒の瞳……、ガリオン帝国王を未だ垣間見た事はないけれど、皇子は母君・ジェイダイトの遺伝子を、強く受け継いでいるんだわ。
周囲の音という音が全て遠ざかっていく。
シーアとシュザックは、まるで周囲には誰も居ないかのように、何かを探るように……お互いジッと見つめ合っていたのだった。