Your Site Title / Tamplate#019
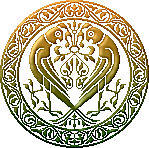
『既成事実、寵愛の一夜』【4】
緋側・アリーシャに頬を叩かれてから、ハーレムでの空気が一掃暗雲立ちこめる事となった。
つまり、シーアへの風当たりが厳しくなったのだ。
それは侍女たちにも言えた。それぞれ徒党を組むかのように、シーアへの嫌がらせが始まった。
回廊や庭で通り過ぎる時、彼女たちはわざとぶつかってきてシーアが膝をついてもクスクス笑うばかり。
また、長椅子に座っていると躓いたフリをして、飲み物を頭からかけたりドレスを汚したり……まさに酷い仕打ちだった。
そういう経験が初めてだった為、シーアは目をぱちくりして驚くほかなかった。
だが、そんなシーアにもたった一人だけ味方をしてくれる侍女が居た。
シーア付きの侍女、リリアン・ウェイだった。
シーアより小柄だが、その美貌はシュザック皇子から寵を受けてる女性たちに引けは取らない。
小柄ながら見事な乳房、細い腰、魅力的に膨らんだ臀部は、女神像のようだ。黒い髪は自然とウェーブがかかり、後れ毛が白い肌に零れて初々しい。
シーアでもそう思うのだから、他の女性からもそう思われてると思う。
だが、彼女たちはリリアン・ウェイをも見下してるような雰囲気があった。
「ねぇリリアン、わたしが彼女たちから非難されるのは……まぁ理由はよくわからないんだけど、どうして貴女までがそういう風に見られるの? もしや、わたし付きの侍女だから?」
「どんでもありません! それは、全てわたくしの家系によるものですわ」
リリアン・ウェイは、シーアの髪を見事に結い上げると、派手にならないよう真珠の髪飾りを挿した。
リリアンの髪の結い方を見ていると、あの日……セリで忠告してくれた女性を思い出す。優しい手つき・触れ方は、全く同じだ。
シャノン・リーは、今どうしてるのだろう?
だが……シーアは、目の前にある問題に集中しようと、その思いを払うように頭を振った。
「……呆れてしまうわ。どうしてそう人を見下してしまうのかしら。同じハーレムで暮らす以上、仲良くするものだと思うのに」
わたしは、明日こっそり出て行く準備をしているから、仲良くするつもりもないけれど……。
「まぁ、とんでもない! ローレルさま……あのぉ、おわかりでしょうか?」
「何が?」
シーアは、リリアン・ウェイの視線を捕えるように、振り返った。
もしわたしが逃げ出す事を知ったら、リリアンはどうするかしら? 一緒にルーガルへの旅に同行し、向こうで暮らそうと言ったら?
「そうですよね、ローレルさまはこの宮に移られてからまだ日が浅いんですもの。詳しい事はわからなくて当然ですわ」
リリアン・ウェイの言葉にハッと我に返ると、立ち上がった。
詳細なんて聞きたくない。でも、何でも知りたがるわたしの性格としては、その事を知りたいと切に願ってる自分もいた。
シーアは顔を歪めて、リリアンの視線から逃れるように、女性たちのクスクスとした笑い声や、噴水の音がする方へ顔を向けた。
知らない方がいい事もある。どうせ、わたしは明日あの通路から外へ逃げ出そうとしているんだもの。
そしてルーガルへ戻る。そうすれば、ガリオン帝国の事は関係なくなる。このハーレムの存在も……シュザック皇子の事も。
皇子の事を思うだけで、胸に刺すような痛みが走った。
この痛みが何だかわからないけれど、知らない方がわたしの為だわ。
ローガン兄様が言っていたでしょ? 何事も追究しなければならない性格が、いつの日か仇になると。
結果、わたしは盗賊ガシュールに捕われ、遥か遠い軍国帝国と名高いガリオンの皇太子のハーレムに居る。
「ローレルさま、ご存じの方がいいですわ。こちらへ来て下さい」
リリアン・ウェイが再び話し始めると、シーアの手首を掴み、ドアへ向かった。
「どこへ行こうと言うの? 庭園に出たら、また侍女や多くの姫たちが、」
「無視すればいいんです! そうよ……何と言っても、ローレルさまは “翡翠の位” を戴いたのも同じなのですから」
全く理由がわからないローレルは、リリアン・ウェイに引っ張られるまま庭園の長椅子に向かった。
シーアが庭園に一歩踏み入れると、一瞬で周囲が静まり返った。
と、同時に憎々しげな視線がシーアに注がれる。
シーアはこの状況に居心地の悪さを覚えていた為、部屋に戻ろうとリリアン・ウェイに視線を向けたが、彼女はシーアを勇気づけるように頷くだけで、噴水の近くの長椅子を指した。
「ローレルさま、あの場所が宜しいですわ。さぁ、気遅れを感じる必要はないんですよ? あの場所で、きちんとこのハーレムについて説明して差し上げます」
空いている長椅子にシーアを座らせると、その横に跪くように腰を下ろした。
すると、初めて庭園に足を踏み入れた時と同じように、真珠色の長いドレスを着た下働きの女性が、シーアの元にお菓子とジュースを置いた。
「あの女性たちは、ハーレムのお世話をする給仕女官です。主に街に住む貿易で裕福になった人の娘たちです。彼女たちに側室同士の派閥に参加する資格はありませんが、各側室に可愛がられている人も居ますのでご注意を」
去っていく女官の背を見ながら、リリアン・ウエィは言った。
「でも、誰に可愛がられているかなんて、わからないわ」
シーアの疑問に、リリアン・ウェイはにっこり微笑んだ。
「それを今からお話しますわ」
「待って! わたしは、」
明日ハーレムから脱出しようと企んでいるから、教えてもらう必要はない……と言いたかった。
だが、それを言うわけにはいかない。リリアン・ウェイと一緒に逃げたいが、彼女を連れ出ワケにはいかないし、秘密を知らない方が後々良い事になるから。
「ローレルさま?」
シーアは歯を食い縛って、頭を振った。
「何でもないわ、続けて」
テーブルに置かれたさっぱりとしたジュースを一口飲むと、リリアン・ウェイが広げた洋紙(→略図←)を覗き込んだ。
「ガリオン帝国皇太子・ホークさまのハーレムは、寵愛を受けている女性が住む場所ですが、同時に側室さまも過ごされています。側室になられるのは数が決まられており、」
「緑晶・緋晶・蒼晶・紅晶・橙晶・黄晶・紫晶・青緑晶・青金晶・菫晶・碧晶・淡晶・白晶と、13の位があるのね」
洋紙に書かれた図形を見ながら、シーアは言った。
「はい、そうです。それぞれの位は宝石の名称から付けられており……、その称号を与えられた側室さまはその宝石を身に着けて、地位がわかるようにするのです。先程の給仕女官の話に戻りますが、彼女たちのペンダントをご覧ください」
シーアは言われるまま周囲に視線を向け、忙しく働く給仕女官の胸元を見た。
ドレスと同じ真珠色の素材をチョーカーとして巻いてるが、そこに揺れ動く石が付いている者も居た。
「つまり、チョーカーに宝石を付けていない給仕女官は、どの側室の保護も受けていないという事ね?」
「はい、そうです!」
リリアン・ウェイはニッコリ微笑んだ。
「側室さまの話題に戻りますが、13の位があるからと言って、この宮に側室さまが13人居るワケではありません」
「でも、」
既に、シーアの存在を無視している女性たちを眺めた。
「こんなに大勢居るのに?」
「ローレルさまったら」
リリアン・ウェイは、クスクス笑った。
「殿下から伽を命じられてからといって、すぐに側室の位を頂戴出来るものではないのですよ。……ローレルさまは別でしたけれど」
その言葉に、シーアは眉間に皺を寄せるぐらい顔を顰めた。
何故わたしだけ別だったの? しかも、リリアンが言うように……伽を命じられたのでなければ、彼の寵愛を一身に受けたワケでもない。
ただ、ひたすらベッドの上で硬直しながら、待ちぼうけを食らわされただけだ。
もちろん、わたしとしては待ちぼうけに遭って良かったと思うけれど。
どうして? どうして、わたしは皆から側室扱いされるというの?
あっ! もしかして……わたしが “緑晶の間” に通された事と関係が? アリーシャさまも、この言葉でわたしの頬を叩いたぐらいだもの。
いったい“緑晶の間” って、何?!