Your Site Title / Tamplate#019
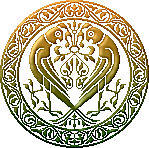
『既成事実、寵愛の一夜』【3】
「ギル……俺はどうしたらいいのかわからなかったんだ」
「わかってる、アルマン。ローレルは……ちょっと普通の女ではないんだ」
ギルは苦笑いを浮かべながら、アルマン伯の肩を抱いた。
この日、アルマンの部下が病気で休んでいた為、たまたまその場に居合わせたアルマンが引受けただけだったのだ。
そして、不運にもローレルの達者な口に負けたのだ。
「そうじゃない。その……ローレルさまが俺に触れられたと殿下に漏らしたとしても、俺は殿下がそれを信じないとわかっていた」
「あぁ、そうだな。殿下はローレルが嘘をついたと見破るだろう」
ギルは、交代要員として来た衛兵にその場を任せると、アルマンを伴って宮殿への外回廊を歩き出した。
「俺は、決してハーレムへの扉を開けるつもりはなかった。だが、」
アルマンは立ち止まると、ハーレムの庭園が覗ける場所で立ち止まると、女性たちを見下ろした。
「ローレルさまが意を決して俺に触れてきた。それも……尋常ではない触れ方だった。男の心を騒がせるような触れ方だったんだ」
ギルは、その気持ちが理解出来るというように頷くと、アルマンと同じように華やかなハーレムの女性たちを見た。
「わかってる。この俺だって、そんな気分にさせられたさ」
アルマンが、ハッと息を飲んだ。
「ギル! ……お前もか?」
表情をピクリとも変えないまま、ギルは頷いた。
「そっか、それなら俺の気持ちもわかってくれるに違いない。……俺は、決して俺からは触れなかっただろう。だが、ローレルさまから漂う可憐な香いと、柔らかな膨らみで胸を擦られた時、このままではいけないと思ったんだ」
ため息をつくと、アルマンは再び歩き出した。
「俺が手を出していないとわかってはくれても、俺がローレルさまの柔らかな感触や香い、体温を感じたのだと知ったら……殿下はきっと冷静ではいられなくと思う。頭では理解してくれても、理性はそうはいかない。そうだろう?」
ギルは、アルマンの言葉が少なからず正しいと思えた。
なぜなら、殿下は……ローレルを “緑晶の間” へ通し、しかも夜が明けるまで手放さなかったのだから。
ギルはアルマンと理解し合った視線を交わすと、共にため息を吐いたのだった。
* * * * *
シーアの躰は、ぐったりするほど疲れていた。
神経を張り詰めながら、いつシュザック皇子が訪ねてくるのか……と、その事ばかり考えて一睡もしていなければ当然の事。
その為、シーアは自室へ戻るなりベッドに潜り込み、侍女たちを外に出すとそっと瞼を閉じた。
だが、昨夜の出来事やハーレムへ戻る時の事を思い出すと、脳が活発に動き出し血が騒ぎ出す。
眠りを求めているのに、心臓が早鐘のように鳴り響き、シーアを揺り動かすのだ。
「……はぁ」
寝返りを打ち、清潔で肌ざわりのいいシルクに頬を押しつける。
ここは娼館ではない……ガリオン帝国皇太子のハーレム。つまり、ここにいる美しい女性たちは、皇子の寵をいただいた者ばかり。
寵をいただいた……という事は、シュザック皇子が彼女たちをあの宮殿へ招き……あのベッドで何度も睦み合ったという証。
「いやっ!」
脳裏に浮かんだ淫らな行為に、シーアは叫びながら飛び起きた。
皇子の陽に焼けた逞しく大きな手が、華奢な女性の躰に触れ、シーアにしたようなキスをここに居る女性たちにもしているのかと思うと、堪らなくなったのだ。
血が沸騰するかのように躰を駆け巡ると、息が出来ないぐらい喉を締めつける。その恐怖から逃れようとすると、思わず喘ぎ声が口から漏れた。
「……何が、嫌なの? 他の女性に触れたようにわたしにも触れたから? それとも、わたしに触れたように他の女性にも触れているから?」
自分の気持ちに戸惑ったシーアは、泣きたいぐらい追い詰められた状態に陥った。
ランドルフ王子の側室ルリさまには、こんな気持ちを抱いた事はないのに……どうして?
やっぱり……関係があるの? ルーガルでは王子にキスされ触れさせても、何とも思わなかった事に。
「わからない……わからないわ。この二つの違いは何なの?」
シーアは頭を振り、膝に額を押しつけた。
――― コンコンッ。
突然鳴り響いたノックに、シーアはハッと面を上げた。
「誰?」
「緋側・アリーシャさまがお越しです」
アリーシャさま? ……でも緋側って?
だが、アリーシャは昨日庭園で優しく接してくれた女性という事もあり、シーアはホッと躰の力を抜いた。
「どうぞ」
扉を開けて入ってきたアリーシャの表情は青ざめていたが、威厳に満ちた仕草でお付きの侍女を下がらせた。
華美な衣装は、アリーシャの美しさを余すところなく引き立てており、シーアは自分が夜着一枚でベッドに居る事に、少々恥ずかしくなった。
「アリーシャさま……こんな姿で申し訳ありません。どうぞおかけになって」
「ローレルさま……」
少し堅い声が響いてきたが、シーアは全く気にならなかった。自分のこの見苦しい姿に赤面し、恥ずかしい思いを味わっていたからだ。
アリーシャさまはきちんと衣服も整えているのに、わたしときたら何て無様な姿を晒しているのだろうか。
「実は、昨夜は一睡も出来なくて……少し疲れを癒そうと思って横になっていたんです」
シーアは、乱れた髪を後ろに撫で付け、少しでも見栄え良くしようとしながら、笑みを張りつけて視線を上げた。
「……えっ?!」
シーアは、あの美しいアリーシャの顔が青ざめ……それでいてシーアを憎々しげに見つめている瞳に驚きを隠せなかった。
何故、そんな風に見つめるのだろうか? 昨日は、あんなに優しく微笑みかけてくれた瞳には、今では冷酷な光が宿り、口元はピクピクと震えている。
「アリー、シャ……さま? どうかなさったのですか?」
事実、シーアはここまで憎々しげに睨まれたり、憎悪を示された事は一度としてなかった。
だから、何故そういう風に見られるのか、わからなかった。
シルクのシーツを払いのけ、ベッドから足を下ろそうとした瞬間、アリーシャは口を開いた。
「では、やはり……皆が噂しているように、ローレルさまは今朝ホークさまの元……宮殿からお戻りになられたのですね?」
ホークさま……つまり、シュザック皇子の事ね。
言葉遣いは丁寧だか、言葉の端々に何か意味深な感情を含ませて話していた為、シーアは慎重にコクリと頷いた。
アリーシャは天を煽ぐように視線を天井に向けて、大きなため息を出した。
「ホークさまは、貴女をどのお部屋に連れて行ったのかしら? ……ホークさまの、自室なの?」
「まさか!」
あの部屋は、どうあがいてもシュザック皇子の自室なんかではない。男性の香いなど一切しなかったし、女性らしさが漂った部屋なのだから。
「シュザック皇子は、そんな事をなさらなかったわ」
「まぁ!!」
まるで悲鳴に近い声をあげるのを聞いて、シーアはビックリしてアリーシャの恐怖に満ちた目を見た。
「どうなさった、の?」
「いいえ! いいえ!」
アリーシャの瞳に宿った恐怖の光は一瞬で消えたが、その後さらに悪意の籠った光が強くなった。
シーアはその視線に身震いし、思わずベッドに座ったまま後ろに身を退いた。
何? 何が起こってるっていうの?!
「それでは、あなたはどのお部屋に? “橙晶の間”? それとも……“淡晶の間”?」
そんなに部屋の名前が重要なのだろうか?
シーアはその質問に疑問を感じたが、あまりにもすごい形相をするアリーシャに対して質問を返すような状況ではなかった。
「……確か、“緑晶の間”だと」
そう言い終えると、アリーシャはハッと息を吸い込み、勢いよく椅子から立ち上がった。
その落ち着きのなさに、シーアはアリーシャの行動を目で追う事しか出来なかった。
アリーシャは、シーアの側へ走るように来ると、大きく手を上げて振り下ろした。
その手は、シーアの頬を思い切り強く叩いた。
「キャッ!」
反動でシーアはベッドに倒れ込む。
ジンジンする頬に触れながら、シーアは上から見下ろすアリーシャを見上げた。
「何をなさるんですか!」
「……わたしは、決して許さない。あなたを……決して許さない! わたしからホークさまを奪えるとは思わないで!」
そう言い捨てると、アリーシャは扉を開いた。
そこには先程の侍女が居たが、その侍女もシーアをきつく睨むと、急いでアリーシャの後ろを追いかけて行った。
「何? いったい何なの?」
シーアはこの状況に全く理解出来ず、あの優しかったアリーシャの変貌に呆然とするしかなかった。
この時、シーアには嫉妬というものがどういうものか、未だ理解していなかった。