Your Site Title / Tamplate#019
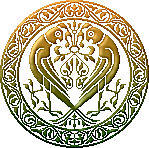
『既成事実、寵愛の一夜』【6】
「……っ、ホークさま!」
女性の甲高い声が、静寂に包まれていた空間に楔を投じた。
いつの間にか強ばっていたシーアの躰から、力が一気に抜けた途端、噴水の音や風で揺れる木の葉、鳥のさえずりが耳に届き始め、喧騒が戻ってきた。
いったい、今……何がどうなっていたの?
シーアがホッと息をついた瞬間、シュザックの後方に居たギルと視線がぶつかった。
グッを奥歯を噛み締めて、この境遇に陥れた人物を睨む。
ギル……もし貴方がわたしを自由にしてくれていたなら。
あの時、わたしが逃げだすのを黙って見逃してくれていれば。
しかし、過去の事を振り返ってもどうにもならない。
そもそも、わたしの愚かさが原因でこうなったのだから。
どうにもならない気持ちを吐き出すように、吐息を一つ吐くと、リリアン・ウェイが腕に触れた。
「ローレルさま、皇太子殿下がこのハーレムにお出でになられるのはとても光栄な事なのです。こういう時は、すぐにお側近くへ寄るものですよ」
側近く?
シーアは思わずプッと吹き出してしまった。
「ローレルさま!」
とんでもない粗相を目にしたリリアン・ウェイは、恐怖から目を大きく見開いた。
そんな事も知らないシーアは、顎を引いてクスクス笑いを噛み殺した。
「だって、側近くと言っても……あんなにハーレムの女性が群がっていたら、場所なんてないも同然じゃなくて?」
「でも、ローレルさまは “緑晶の間” に通された方なのですよ!」
「やめて!」
リリアン・ウェイが悪いわけではない。
彼女はハーレム内で孤立したわたしの側で仕え、親身になってくれた。
彼女の事は、大切な友だと思っている。
でも、何かにつれ “緑晶” という言葉を発しないで欲しい。
わたしは、そんな称号を欲しいとは思ってもいなし、ましてやシュザック皇子の側室になる気もさらさらない。
ただ、この国から逃げ出し……元の……安全な場所に戻りたいだけ!
「…… わたし一人ぐらい側に居なくても、誰も気付きはしないわ」
「そんなっ、」
「誰が “気付かない” と?」
心地好く耳に響くバリトンが側で聞こえた途端、シーアの背筋に震えが走り、一気に鳥肌が立つのがわかった。
シーアは、傍目にはわからないよう深呼吸しながら振り返った。
「昼間っからハーレムに入り浸るようでは、皇太子としての名は……もしかしてただの飾りかしら?」
女性たちの鋭く息を吸い込む音が、シーアの耳に届いたが、シュザックから視線を逸らさなかった。
彼を見ているだけで……あの漆黒の瞳で見られるだけで、頬が熱くなってくるのがわかる。
だが、これは戦いとでも言うように、シーアはシュザックの威厳に真っ向から立ち向かった。
そんなシーアを、シュザックは口元を緩めて微笑んだ。
「何だ? ……明け方まで俺に拘束されたのを怒っているのか?」
再び鋭く息を吸い込む音が聞こえたが、シーアはシュザックの言葉の意味に気付くと、羞恥心から躰を震わせた。
頬がほんのり染まっていくのがわかっていながら、シーアはただシュザックを睨み付けた。
「酷い人……、本当に酷い人! わたしの眠りを妨げる事を知っていながら、あんな事を!」
「ローレルさま!」
リリアン・ウェイは顔を真っ赤にさせながら、シーアの言葉を閉ざそうと咄嗟に口を挟んだ。
そんなリリアン・ウェイを、シーアは苛立ちを含んだ眼差しで見つめた。
「リリアン!」
「ローレルさま、 ……お二人で親密に過ごされた内容を公の場で口にするのは、」
「親密?!」
あれのどこが親密だっていうの? わたしに用はなかったのに、一晩中彼はわたしを拘束したのよ。しかも、恐怖心を植えつけようとしたわ!
シーアは、恥ずかしそうにしているリリアンからシュザックへと視線を向けた。
そこに浮かんでいる楽しそうな表情を見て、またも怒りが込み上げる。
だが、シュザックの側にソッと近寄った緋側・アリーシャの憎々しげな瞳にぶつかると、まるで冷や水をかけられたように、憤懣やるせない気持ちは急速に冷えていった。
何……、どうして?
シーアの表情を何一つ見逃さなかったシュザックは、手を伸ばしてシーアの柔らかな頬に触れた。
「ローレル、すまなかった。かなり酷使させたようだな」
酷使? 何が言いたいの?
突然触れられた事と、意味不明の言葉に、シーアは動くことすら忘れていた。
そんなシーアに、シュザックは笑みを浮かべながら親指でシーアの愛らしい唇をゆっくり撫でた。
「眠れなかったのが、そんなに辛かったのか? 俺の事が脳裏から離れず、身悶える事が出来ただろ?」
シーアは、シュザックが何を言ってるのかその心理がわからなかった。
わかるのは、彼の指が唇に触れている……ただそれだけ。
喘ぐように喉が上下が動くのを見たシュザックは、満足気に腕を下ろした。
「安心しろ。ローレルには休息を与えてやる。次はもっともっと心身共に疲労困憊するのだから。……アリーシャ!」
「はい、ホークさま」
シュザックは、シーアの瞳を覗き込むようにしながら口を開いた。
「今夜、俺の元へ来るように……」
「はい、ホークさま!」
アリーシャの口から歓喜の声が漏れる。
シュザックは、ジッと反応を探るようにシーアだけを見つめていた。
シーアは、シュザックの瞳に魔法をかけられたような錯覚に陥っていたが、彼がアリーシャに言った言葉がどういう意味なのか悟ると、何とも形容しがたい思いが胸に込み上げてきた。
あの時と同じだ。シュザック皇子の宮からこのハーレムへ戻ってきた時、胸に渦巻いた思いと。
あの唇が……他の女性にも優しく動くのだとわかった時に感じた……胸を焦がすような、それでいて胸を刳るような痛みが、再びわたしに襲いかかる。
イヤ、イヤ! 胸が痛い!
シーアは、痛みが瞳に宿るのを恐れるように、サッと俯いて瞼を閉じた。
「ローレル?」
シュザックの声が問いかけるように上から降り注いできたが、シーアはその声に聞く耳を持たず、ドレスを軽く持ち上げると身を翻した。
この泣きそうになる程の思いを抱いて、シュザックの顔を見る事は出来なかったからだった。
この時、もしちょっとでも振り返ってシュザックの顔を見れば……何らかの答えが見つかったのかもしれない。
だが、シーアは自分の部屋へと姿を消した為、そのチャンスを得る事はなかった。
その日の夕方、ハーレムはアリーシャを中心に華やいでいた。
シーアはその様子を、開け放たれた窓から聞こえてくる話し声を自室で聞いていたのだ。
アリーシャが、今夜シュザックから寵愛を受けるのかと思うと、ムカムカとした思いが湧き起こると同時に、大声で泣きたくなるような感情が湧き起こってくる。
こんな思い、イヤ! したくないわ! ……何で、こんな気持ちを味わわなくてはならないの?
我知れず立ち上がると、シーアはそっと回廊に面した窓から騒がしい緋側の部屋を見つめた。
見事なルビーが耳元で揺れているその姿は、女のシーアから見てもとても美しく見えた。
それもそうよね。初めて庭園でお会いした時、何て綺麗な人なのかしらって思ったぐらいだもの。
あの時優しかったアリーシャから、どうして憎まれるようになったのか、今ははっきりとわかっていた。
リリアン・ウェイから見せてもらった洋紙が、それを物語っている。
あの女性も言ってたわ。このハーレムで、一番格の高いのがアリーシャさまだって。
そこへわたしが……ここでは身分すらないわたしが “緑晶の間” を与えられたから、だからアリーシャさまは……。
だからと言って、あんな態度が許されるべきではないと思う。
でも、わたしはそれを進言する立場にはない。
何故なら、わたしはこの国の民ではないから。ここから逃げ出そうと、国へ戻ろうと画策しているから。
美しく着飾ったアリーシャが、気品漂う仕草で皇太子の宮へと続く回廊を歩き始めるのを見てから、シーアはそっと部屋から抜け出した。
わたしは、やるべき事をするだけ。ここに居たくないのなら……そうするべきでしょ?
だんだん視界がボヤけていくと、鼻の奥がツンとした。
同時に、涙が溢れて頬に流れ落ちた。
それを手の甲で拭うと、シーアはこの気持ちに蓋をし、前だけを向いて歩いた。
“ある物” をこっそり拝借する為に……。
シーアの脱走劇は、誰に知られる事もなく……着実と進行していたのだった。