Your Site Title / Tamplate#019
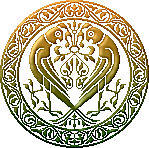
『招待=ホークの正体』【3】
すごい厳重な扉……
まるでハーレムにいる女性たちを逃がさないようにする為みたい。
バカな……何を考えているの、シーアローレル!
ココはハレームなんかじゃないわ。……まぁ、似てるようなモノではあるけれど。
でも、それにしても衛兵が扉に立ち、女性たちのいる館を繋ぐ回廊を監視しているなんて、どういう事?
逃げ出さないようにする為? 娼婦という仕事を全うさせる為?
侍女に伴われながらも、シーアは周囲への観察をし続けた。
「ここより、主君ホークさまの宮になります」
大きな扉が開かれると、一緒に来た侍女は後ろに下がった。
そして迎えに来た侍女だけが、共に中へ入った。
「あの……侍女たちは?」
「彼女たちは、この宮へ入る資格がございません。ホークさまが決められた方、望まれた方だけが、この宮へ入る事が許されます」
という事は……あの人は威張ってるって事ね。
何て腹立たしい男なの!
わかってるのかしら。こうやって大きな……宮殿とも言えるような宮に住居を構え、衛兵を雇えるという事は、あそこに居る娼婦たちが男に躰を開いて……大金を稼いでくれてるからという事を。
確かに、手腕がなければここまで成功する事は難しい。
男にとって、娼婦という存在が必要だという事も……多少はわかる。
だけど、それは女たちの気持ちを踏みにじってる。
角を曲がった時、自然と光が見える外へ視線を向けた。
「あっ!」
シーアは思わず足を止めた。
なんと、あの女性たちの住む庭がまる見えだったのだ。
篝火で白亜の館が煌々と輝き、神秘的にさえ見える。
館? ……ううん、違う! 大きな宮殿だ。
何て事なの。わたしの行動範囲なんて、たった数歩に等しいじゃない。
女たちの住居の周囲には、いくつもの宮が存在しているし……外壁だと思ってた壁は実は内壁だなんて!
シーアは、喉を手で押さえて荒い息を整えようとした。
ダメ、諦めてはダメよ! わたしが見つけたあのドアは、絶対外に通じてる筈。でなければ、どうやって彼らが厳重な宮殿に入って来れるというの?
しかし、現実を目の当たりにしてしまったシーアは、混乱の渦中にいた。
心臓は一層激しく高鳴り、ふらふらとさえする。
「……大丈夫か?」
耳のすぐ側で、低いバリトンの声が響いた。
躰が硬直したかと思うと、一気に火照りだした。
シーアは、勢いよく振り返った。
目の前には、あの男が居た。
わたしを、買った男……無作法な仕草で唇を求めた男!
今日も黒い衣装に身を包んでいた。
それが……何と似合う事か。
引き寄せられるような力から逃れるように、視線を逸らせると、そこには侍女らしき人物はもういなかった。
遠くに、護衛の男が見えるだけ。
シーアは、ゴクリと唾を飲み込むと、再び視線を合わせた。
「いったい、何の用なの?」
彼は、シーアの躰を舐めるように視線を這わした。
たったそれだけで、躰に触れられたような錯覚に陥る。
イヤ、やめて。わたしを混乱させないで。
彼の手が伸びると同時に、シーアは一歩後ろに下がった。
だが、シーアの歩幅など腕の長さでカバーし、彼は華奢な腕を掴んだ。
自分の肌が白い……と感じた事は一度も無い。祖国では、太陽を浴びるのが好きだったし、娼館にはもっと白い肌の持ち主がいるからだ。
でも……
シーアは、自分の腕を掴む男らしくて大きな手と関節に魅入った。
陽に焼けてる腕が、逞しくさえ思える。それに、彼の腕と比べて、何と自分の腕は白いなのだろうと。
「……痛いわ」
痛いどころが、心臓が激しく高鳴ってる。
視線を上げると、彼はシーアの盛り上がった乳房を見ていた。そして、ゆっくり視線を上げて、シーアの言葉は本当でない事を知っていると言わんばかりに、眉を上げた。
何なの、この男! 無礼で、無作法で……マナーがなっていない!
だが、怒りを口にする前に、彼がシーアの腕を引っ張った。
「あっ!」
その力に負けて、彼の側へ引き寄せられる。
裾は彼の足に触れている。躰は、触れる寸前だ。
頬が染まっていくのがわかる。こんな触れ合い、今まで何度も経験があるし、それ以上の事でも、平然とあしらう術を身につけていた。
にもかかわらず、その術さえ頭の中に浮かんでこないなんて!
「こんなところで話すより、室内(なか)での方が寛げる。さぁ」
こちらの意思を気にせず、彼は整えられた一室へと誘った。
大理石の上に絨緞が敷かれ、その上には二人では食べきれない程の料理が置かれていた。
大きなクッションが2席設けられている。
これが何を意味するのか、わからないシーアではない。
国は違うが、正式な作法はテーブルで摂るとされている。
床に絨緞を敷き、そこに座っての会席は……親密さが含まれてる。
シーアも幾度となく気軽に座って、家族と共に食事をしてきたが、宮殿では決して床になど座る事はなかった。
皇太子ランドルフとの食事でも、こんな風に寛ぐ事は決してなかった。
これは、侮辱だわ。買った娼婦になど……敬意を払う必要はないという事なのね。やっぱり……国で噂されていたとおり、ガリオン帝国は戦で土地を奪ってきた……野蛮な国なんだわ。だから礼儀すらなっていない。
シーアは、彼が上座に座るのを待って、隣に設えたクッションへ座った。
彼の目は急に細められ、シーアを凝視した。
どう? 奔放に育てられたわたしだけど、きちんと母さまから躾は受けたわ。ルーガル王国宰相の孫娘として……わたしは、きちんと……。
肩書きを思い浮かべた瞬間、シーアは胸が締めつけるような痛みを感じた。
それは……綺麗な躰のままで、二度と親族に会えないという事だろうか?
わたしが娼婦として買われたとしれば、お祖父さまや、父さま、それに兄さまたちは絶対怒り狂うわ。もしかして、戦を仕掛けるかもしれない。
ダメ、それだけはダメよ! 王は絶対お許しにはならないわ。王の娘ならいざ知らず、わたしはただの宰相の孫娘だもの。
この事は、絶対知られてはいけない……。
家族の為にも……そして祖国の為にも!
「ローレル」
侍女から杯に酒を注いでもらいながら、彼は口を開いた。
シーアは顔を動かし、彼の視線を真正面から受けた。
「出身はルーガルという事だったが、宮殿に仕えていたのか?」
「……いいえ」
そう、確かにノーだ。王女の侍女としての話は持ち上がった事はあったが、全て水晶球のせいで、その話は泡と化した。
いずれは皇太子の正妃となる器という事で、王族のように扱われていたからだ。
確かに、先祖の血を辿っていけば王族の血筋を引いてるとも言える。
だが、今の称号は貴族のみ。
その事を、この男が知る筈もない。だが、彼は目を細めて探るように見つめてくる。何を考えているのだろう? 何を思っているのだろう?
「そうか……と、その言葉を鵜呑みにする程、俺はバカじゃない。それにしても、」
彼が大きな手を伸ばしてきた。
身を引きたかったが遅かった。彼に顎を掴まれて、前へ倒れそうになる。
「さすがルーガルの女だな。この国の女や、周辺隣国の女たちとは違う美しさを持っている」
「やめて!」
身を捩り、彼の手から逃れながら睨み付けた。
「……? おいっ?!」
彼の手が再び顎を捕えようとする。
シーアは躰を捩りながら、瞼を閉じた。
「こんな駆け引きのような事は、やめて欲しいわ! ……はっきり言って。わたしをいつから働かせるの?」
「働く?」
シーアのその言葉に、彼は戸惑ったようだった。
何を今さら。
シーアは振り返ると、彼の眉間の皺を見つめた。
本当に、戸惑ってるようだった。
今までの傲慢な態度には見られなかった仕草だった為、逆にシーアの憤りが少し弱まった。
「……そうよ。わたしは、いつからお客のお相手をするの? いつからわたしは……娼婦となるの?」
最後の言葉を言う時、心ならず涙が込み上げてきた。
覚悟していたのに、そうなるものだと頭ではわかっているのに、やはり張り裂けそうな程の痛みが心を襲う。
涙なんか流さない! この男の前では絶対流さない!
しかし、シーアの思いとは裏腹に、彼は大声で笑い出した。
「何を言うかと思えば……娼婦! いったいどこからそんな考えが浮かんだんだ?」
杯からお酒が零れるのも気にせず、彼はシーアに顔を寄せた。
「俺のハーレムに居る女を他の男にくれてやるわけないだろ?」
ハーレム?
「それとも、ローレル……お前は俺が相手では嫌だと言うのか? 他の男たちを相手する方がいいとでも? ……ガリオン帝国・皇太子、シュザック・ホーク=ガリオンの寵を受けたくはないと?」
シーアは、彼が放った言葉に顔を青ざめた。
彼……シュザックがこの国の皇太子だなんて。ルーガルの王女を正妃にと望んだ人だなんて……何て事なの!
シーアが気絶せず耐えられたのは、思わず両手を握り締めた事で、兄から貰った石が掌に食い込み、痛みを感じていたからだった。