Your Site Title / Tamplate#019
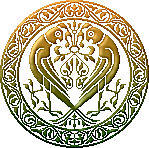
『一筋の光、暗黒への道』【7】
薄暗い路地裏は、太陽が沈むにつれ闇に包まれていく。
シーアは早く “ラムジーナの交易亭” に辿り着きたかったが、心のどこかで今日はもう無理だとわかっていた。
あの商人が、ラムジーナは早めに店を閉め、酒場へ行くと言っていたから。
大通りは篝火が焚かれ始めた為、シーアでもどちらに行けばいいのかわかった。
その明かりはまだ針の穴のように小さかったが、遠くに居ても賑やかな声は微かに聞こえてくるからだ。
シーアは、陰の世界から陽の世界へ導かれるように、自然とそちらへ足を向けた。
だが、重い荷物を引っ張ってるかのようにその足取りは重く、傍目から見ると殆ど立ち止まっていると言っていい程、歩みは遅かった。
それもその筈、朝から固形物を口にしていない上に、極度の緊張と疲労が今になって襲ってきたからだ。
逃げようと決めていたのなら、きちんと食事を摂るべきだったわ。
でも……まさか、こんなに時間がかかるとは思ってもみなかったから。
わたしの予想では、宮殿から逃げ出してすぐ宝石をお金に換え……今頃はガリオン帝国の首都から郊外へと馬を走らせてる頃だったのに。
シーアは、裾がドロドロになった女官のドレスを見下ろした。
光沢を放つ真珠色のドレスは、見るも無残に汚れて糸まで出ている。
もちろん、マントも悲惨な状態だわ。
でも、その上に羽織った服は、汚れていはいない。それだけでも良しとしよう。
何故こんな時に、着てる物の心配をしなければならないのか、シーアにも全くわからなかった。
本当なら、今日中に行動を移すべきだってわかってる。
でも、わたし……もう動けないわ。
とにかく宿屋がどこにあるか訊ねて、宝石を担保にして泊めてもらうしかない。
そこで手紙を書いて、宿屋の主人に預け、集配しに来た人に渡してもらえれば。
宿屋と思っただけで、シーアの脳裏に熱々のスープ・焼き立てのパン・芳醇な赤ワインが浮かんだ。
あぁ、お腹が空いたわ。
空腹を満たしたいのなら、歩かなければ。今頼れるのは、自分自身だけなのだから。
歯を食い縛って、視線を前に向けた時、今まで目印にしていた大通りの明かりが消えていた。
「えっ? 何で?」
今までは明るく見えていたのに、どうして?
シーアは、目を凝らすように前を眺めて……初めて誰かに囲まれているという事がわかった。
一人ではない息遣い、酒臭い口臭、汗にまみれた男臭い体臭が、シーアの耳と鼻に届いた。
こんな風に囲まれているというのに、シーアはあの日と同じだと思った。
ルーガルの宮殿で、すぐ上の兄・ユエンの元から飛び出し、一人馬を駆けてルードリア湖へ行って……捕まった時と。
あれからまだ2ヶ月にもなっていないというのに、もう一年ぐらい経った気がする。
「宝石を渡しな!」
その声で、シーアは物思いから覚めた。
本来なら怖がってもいい筈なのに、何故か脳と躰が別々な考えを持っていて集中する事が出来なかったのだ。
だが、その覆面を被った男の言葉に、シーアは無表情に視線を向けた。
疲れ切った躰に緊張が走り、脳が活発に動きだす。
何故この男が宝石の事を知ってるの?
その時、男が移動した事で大通りの光差し込み、彼らが手に握っている短剣に反射してキラッと光った。
そこで初めて、シーアは唾をゴクリと飲み込み、忍び寄る恐怖に躰を強ばらせた。
「早く出せ!」
リーダーと思わしき人物が、もう一度発した。
もし逆らったらどうなる? ……今は体力が落ちているから、思い切り走っても捕まるだろう。
それに、 “宝石” と言う以上、何故かはわからないけれど、わたしが持っている事を知っている。
でも、大事な宝石を渡す事は出来ない。渡してしまったら、わたしはいったいどうやってルーガルへ戻ればいいっていうの?
あぁ、わたしったら何て考えなしなの! 全ての宝石を一緒の袋に入れておくなんて……。 でも、今までそんな事を考える必要もなかったから。
「出さないんなら、やれ!」
「えっ?」
取り囲むように静止していた男たちが、シーアに襲いかかってきた。
「キャァーー!」
足がもつれてしまうのも構わず、シーアは逃げようと彼らとは反対方向へ……あの暗い路地へと走り出した。
「捕まえろ! 絶対逃がすな! 宝石を奪え!」
イヤ、イヤ! 絶対イヤよ!
シーアは目の前に広がる闇と、覆い被さってくるような壁に躊躇し、途中で足を止めた。
振り返ると、すぐ側まで男たちが来ていた。
路地に置いてあった大きな木箱を倒して道を塞ぐと、先ほどの路地とは違った道を左折し走った。
「っのやろ!」
舌打ちと苛立たしい声が、シーアの真後ろで聞こえる。
ダメだ、もうダメだ……、わたし……国へ帰られない。
父さまや母さまの……所へ戻れない!
強く肩を掴まれると同時に、思いっきり地面へ押さえつけられた。
双眸から涙が零れると、嗚咽が漏れた。
「言っただろ。宝石を渡せと」
あのリーダー格の覆面男が、シーアを抑え込み、その二人を囲むように男たちが陣取った。
「やめて……」
抗うシーアの腕を掴むと、男はシーアのマントを押し開き、腰に縛りつけた袋をもぎ取った。
「確認しろ」
男は、側に居た男に袋を投げつけた。
「返して! ダメ!」
「す、す、すごい……こんな宝石は初めて見た」
驚愕の声が頭の上から降ってきたが、シーアは目の前に居る男に縋るように見つめ返した。
「お願い、一つか二つ……だけでいいから返して。それがないと、わたしは家に戻れないの! 旅費がないのよ、お願いだから!」
覆面の穴からは目しか見えないが、シーアは情けに縋ろうと必死に頼んだ。
だが、シーアの言葉を無視すると、その男はシーアの喉元に手を伸ばした。
絞め殺されてしまう!
恐怖から小さな悲鳴が漏れたが、その男は気にすらしない。
「盗むんじゃないぞ。一つでも盗んだら、どうなるかわかってるんだろうな!」
周囲の男たちに向かって投げられた言葉だったが、シーアから目を離そうとはしなかった。
両腕を掴まれて身動き出来ないシーアは、彼の手が喉に触れられると瞼をギュッと閉じた。
瞬間、首に痛みが走った。
「これも戴いておく」
彼が何を引きちがったのか一目瞭然だった。
ピアスと対になっていたペンダントだ。
服の中に入って見えない筈なのに、どうしてわかったのだろうか?
だが、その答えを導き出す前に、男はさらに行動を移した。
シーアの指に嵌まっている指輪まで抜き取り、側の男に渡したのだ。
「ダメ! それだけは返して! それは……それは……兄からのプレゼントなの。この世に一つだけしかない指輪なの!」
「ダメだ」
その一言で、シーアの躰から力が抜けた。
ダメだわ……わたしが何を言っても、もうどうにもならない。
宝石は返ってこない、旅費はない……泊まる事さえ出来ない、家族の元へ帰る事が出来ない!
「どうして……どうしてわたしなの?」
どうしてわたしが狙われる事になったの?
「……世間知らずなお嬢さんだ。いいか、無闇に人を信じて見せびらかしたお前が悪いんだ」
見せびらかした? 無闇に人を信じた?
彼は、もう宝石は持っていないか、シーアの躰を無造作にまさぐり始めた。
だが、その手が小ぶりだが形のいい乳房に触れる時は、触れ方が違った。
「やめて、イヤ、触らないで!」
まるで感触を確かめるように、反応を引きだそうとするかのようなその触れ方に、シーアは寒気を覚えた。
そう、ランドルフ王子が欲望を抑えられずに触れた時と同じだったのだ。
「いい躰をしてる、反応もいい。……旅費がないのなら、俺の家に泊まればいい。代金は、お前の躰で払ってもらうとしよう」
彼が荒い生地の上から、乳首を擦った。
心地のいいベッドを約束すると宣言しているかのように。
彼が顔を近づけてきた。
その瞬間、捕まれていた手が自由になった。
シーアを拘束していた手は、いつの間にか頬を撫でている。
「柔らかい肌だ」
この男は……宝石まで奪っておきながら、わたしまで奪おうとでも言うの?
こんな男に触れられるぐらいなら!
シーアは自由になった手で、彼の顔を叩いた。
すると、覆面が外れて彼の顔が見えた。
まだ若く、20代と言っていい。頬には傷があるが、その顔は女性から好まれる彫りの深い顔だった。
シーアの突然の行動に、彼は驚くと同時に怒りを漲らせた。
に、逃げなくちゃ!
この時、シーアは殺されると思い、がむしゃらに彼を押し倒した。
周囲に居た男たちは、この男がシーアを女として扱い始めたので、少し距離を開けていた。
その隙を狙って、シーアは走り出した。
大通りと違ってそこは薄暗いが、そこまで走れば、周囲の人に助けを求める事が出来る。
シーアは、追ってくる気配を感じながら、がむしゃらに走った。
見知らぬ男に犯されるぐらいなら、力尽きて……死んでもいいとさえ思った。
あと、もう少し!
初めて路地裏ではなく、開け放たれた通りへ出られると思うと、シーアはホッとした。
だが、「止まれ! 待つんだ!」という声が聞こえた瞬間、シーアは逃げなければという思いで、周囲を見る事もなくそのまま走り出した。
どうしても捕まりたくなかったのだ。
「危ない!」
その声で、シーアはハッと立ち止まった。
気付けば、カラカラと車輪の音と蹄の音が聞こえていた。
我に返り、横を見た瞬間……馬車がシーアに向かって勢いよく走ってくるところだった。
逃げなければ!
そう思ったが、立ち止まった足は動こうとしない。
御者の顔が恐怖で引き攣るのを見ながら、シーアの躰は衝撃と共に宙に舞い上がった。
痛みなどは一切なかった。
これで……もう終わりだと、楽になれると……そう思ったからだ。
脳裏には、一瞬で家族の顔が浮かんだ。
わたし……家に戻れなかった。戻りたかったけど、もうダメみたい。ごめんなさい。
なんて短い一生だったのだろう。しかも、異国でこの命を失うなんて。
わたしには……わからなかった。
たった一筋の光を求めて前だけを向いていたのに、それが暗黒の世界へ続く道だったなんて。
後悔の念が込み上げてくると同時に、シーアの瞼はゆっくり落ちた。
薄れていくまさにその瞬間、シーアの脳裏にシュザック皇子が現れた。
食事をしながら楽しそうにシーアに微笑んだかと思うと、あの黒い瞳で真摯にジッと見つめてきた表情だった。
「……皇子」
そのままシーアの意識が途切れた。
その後、舞い上がった躰は激しく石畳に叩きつけられた。
シーアはピクリとも動かなかった。
その場から逃げるように馬車が走り出すと、事故を目撃した一組の親子だけがシーアに駆け寄ってきた。
シーアを追いかけていた男は闇に紛れて、その場から姿を消していたのだった。