Your Site Title / Tamplate#019
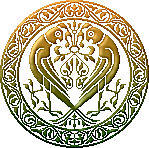
『一筋の光、暗黒への道』【2】
シーアが、自分に与えられた部屋へ戻ろうとしたその時、ハーレム内がざわざわし出した。
何が原因なのか、それを見極めるように視線を周囲に向けると、緋側アリーシャが、堂々と緑が溢れる庭園へ出て来るところだった。
アリーシャの地位を証明するように、白い胸元で鎮座する大きなルビーのペンダントは、誰もがその豪華さに目を奪われるような輝きを放っていた。
もちろんシーアもその宝石に吸い寄せられるように立ち止まった。
そんなシーアに、アリーシャはすぐに視線を向けた。
その瞳には一瞬で冷たい光が宿ったが、その直後艶やかな笑みを浮かべてシーアの方へ近寄ってきた。
だが、立ち止まる事はなくそのまま横を通り過ぎたが、彼女は毒を吐く事を忘れなかった。
「ホークさまったら、朝までわたくしを手放して下さらなかったのよ。きっと、わたくしの前の方が、殿下を十分に悦ばせる事が出来なかったのね」
シーアは血の気が引いていくのがわかったが、アリーシャを見ようとはせず前だけを向いていた。
もし見ていれば、アリーシャの気持ちが鏡のように映し出された表情を垣間見る事が出来たかもしれないが、シーアにはまだそこまでの余裕はなかった。
自分の気持ちが一切わからないのも事実だったが、アリーシャの言動が最初の出会いの時と比べて、だんだんひどくなってきたからだ。
クスクス笑い声を漏らしながらアリーシャが去ると、シーアは歯を食い縛って自室へ向かって歩き出した。
もう関係ないんだから! わたしはこのハーレムも、ガリオン帝国の事も……全て忘れてしまうんだから。
心は、愛する家族の元へ……ルーガルへ飛ばすのよ。
シーアは、遥か遠いルーガルを思いながら、青い空を見上げたのだった。
太陽が真上に届く前のこの時間、女官たちは大忙しだった。
洗濯もあれば掃除もある為、まるで誰かに追い立てられるように躰を動かしている。
リリアン・ウェイも例外ではなく、シーアが庭園でゆったり過ごしている事を前提に、花を生けたりしている頃だろう。
シーアは、この時とばかりに今朝着替えたドレスを脱ぐと、昨夜勝手に拝借していたドレスを身に纏った。
それは、下働きの女官が着る質素なシルクのドレスだった。
髪を解いて宝石を外し、首筋のところで二つにわけて緩く結ぶ。
用意していた袋を手に取った時、今朝より少し重くなっているように感じたが、時間が惜しい為、確認する事もなく腰のベルトにその袋を紐で結んだ。
鏡の前で自分の顔を眺めた時、今朝リリアン・ウェイが譲らなかったエメラルドの宝石が目に入り、それを取ろうと手を上に上げた時、後方で大きな音がした。
シーアが慌てて振り返ると、そこには目を大きく見開いて青ざめているリリアン・ウェイが立っていた。
「リリアン!」
何と言って誤魔化そうか考えている時、リリアン・ウェイはシーアの服装を眺めて悲しそうにその事実を把握していた。
「……やっぱり、おかしいとは思っていたんです」
リリアン・ウェイは、手に持っていたカゴを下に置くとシーアに近付いて跪き、ドレスの裾に触れて見上げてきた。
「失礼ながら申し上げます。バカな考えはどうぞお捨て下さい。このハーレムから……殿下の寵愛を受けながら逃げきれるなんて、そんなのは不可能です!」
「いいえ!」
シーアは何度も頭を振った。
「何が不満なのですか? 殿下から “緑晶” の位を戴き、ジェイダイトの称号まで手に入れたのですよ。ハーレム内でのトップの地位、殿下から最高の寵愛を戴く身となったのに、どうしてお逃げになろうとするのですか!」
リリアン・ウェイの瞳から、涙が溢れて頬を伝う姿を見ていると、シーアはやりきれない気持ちでいっぱいになった。
誰かを悲しませるのは好きではない。
というか、今までこんな風に自分の事で誰かが泣いた事はなかった為、シーアは本当に狼狽えていた。
「やめて……やめて!」
シーアは手触りのいいシルクの生地を掴むと、身を翻してベッドに置いていたマントを手に取った。
「ローレルさま! おやめ下さい。例えハーレムから出られたとしても、鉄壁の守りを誇るガリオン帝国から簡単に出る事は不可能です! それに、殿下に捕まったら、いったいどうなるかお考えになられたのですか?」
「……ごめんなさい」
ギュッとマントを掴んで振り返った。
「わたしは、ここでは幸せになれないの。わたしは自分の国に戻って、心配させてしまった家族の元へ戻りたいだけ」
リリアン・ウェイは激しく頭を振った。
「いつまでも家族の元に居られるのは、上流階級の姫だけです。普通は適齢期になれば、嫁ぐか奉公に上がるしかないのですよ。ここにいれば殿下の寵愛を一身に受けて、いつの日か殿下の第一皇子を、」
「やめて!」
恐ろしいその言葉から身を守るように、シーアは両手で我が身を抱いた。
シュザック皇子の子供だなんて……。
だが、その言葉を実感した途端、お腹の奥深いところが熱くなってきた。
シーアは頭を振った。
わたしと皇子はそういう関係ではない。
それに寵愛どころか、彼はわたしを虐めて楽しむ……そういう人なのよ。
「……そろそろ行かなければ」
輝く太陽の位置から察するに、わたしは早く行動を起こさなければならない。
「ローレルさま! わたしは、この事を殿下に報告する義務があるのですよ? そうすれば、殿下はローレルさまをお許しにならないかも知れません。どうか、わたしにそんな役目を押しつけないで下さいませ!」
「ごめんなさい、本当に……ごめんなさい。わたし、リリアンの事は好きよ。とても良くしてもらったって感謝もしている。だけど、ここにはいられない、シュザック皇子の元にもいられない! ……わたしには、国にフィアンセがいるのよ」
実際は形式張った儀を行ってはいないが、事実……シーアは 〔水晶球の祈り〕 のせいで、ルーガル王国のランドルフ王子の正妃になる女性として、幼い頃からそういう風に躾られ教育も受けてきた。
国に戻れば、ランドルフ王子の元へ嫁ぐ事になるかもしれないが、もし盗賊に攫われた事が公になっていれば……傷物として嫁ぐ必要はないかも知れない。
そう思った途端、シーアの心に花が咲いたように、一瞬で暖かい風が流れてきた。
ランドルフ王子の正妃にならなくても……いい?!
「行くわ」
シーアはリリアン・ウェイに背を向けると、扉を開けた。
「ローレルさま! ローレルさま!」
泣き叫ぶ声を聞くだけで胸が痛んだが、シーアは周囲の下働きの女官に混じるように、視線を下げながら問題の戸口へと向かった。
ごめんね、ごめんね……リリアン。
わたし、本当にここには居られないの。
どす黒い渦巻くような側室たちの気には耐えられないし、それに……わたしを変にさせてしまう力を持った……シュザック皇子の側には居たくない!