Your Site Title / Tamplate#019
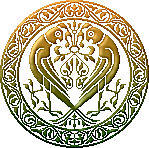
『既成事実、寵愛の一夜』【1】
鳥のさえずりが聞こえ始めると、カーテンの隙間から光が差し込み始めた。
夜が明けた……
シーアは歯を食い縛り、この屈辱とも言える一夜に怒りを覚えて身を震わせた。
だが、逆に安堵したのも事実だった。
ガリオン帝国・皇太子、シュザック・ホーク=ガリオン……あの人はいったい何を考えてるの? わからない、わたしにはわからないわ。
肌触りのいいシルクの上を滑り、そっと天蓋のカーテンから抜け出すと、素足のまま床に降り立った。
分厚いカーテンを引き、まるで下界を見下ろすように、外の景色を眺めた。
昨夜見たより、もっとはっきりと宮殿が見渡せる。
塀で囲まれた宮殿の向こう側には、広大な街が見えた。
あそこに辿り着けるだろうか? そして、ルーガルに戻れるだろうか?
太陽の光が、シーアを包み込むように降り注いでいた。
その為、肌を全く隠さない衣が透けて露になっていたが、シーアは全く気にしていなかった。
誰に観られる心配もなかったからだ。
寂しそうに微笑むと、シーアはここに来る為に着たドレスに着替えようと、そっと肩にある生地を下げながら、部屋の中央に向かって歩き出した。
* * * * *
――― 数時間前。
この“緑晶の間” がいったい “何” を意味するのか、シーアには全くわからなかった。
だが、一歩足を踏み入れた途端、特別な部屋だという事はすぐにわかった。
部屋自体のアクセントはエメラルド色で装飾され、さりげなく置かれた調度品や置物は、部屋の雰囲気を……豪華というより気品があり、とても清純且つ女らしい感じを醸し出していたからだ。
例えば、ベッドを覆うように天蓋から垂れ下がった生地はとても薄く、淡いエメラルド色が……独特の色香を漂わせている。
ベッドの細工も精巧で、玉座のようにエメラルドが填め込まれている。
まさしく“緑晶”の部屋と例えられるだろう。
見た限り、きちんと埃は取り払われてる……つまり、ハーレムの女性を泊める部屋という事?
そして、そして……このベッドは……。
躰が勝手に火照り出した事に戸惑いながら、シーアは侍女に促されて奥へと向かった。
そこには、部屋付きの湯殿が設けられていた。
本来なら湯殿専用の別棟がある筈なのに、特別に誂えられてるなんて。
衣装を脱がされて、香料を浸した湯に入らされると、有無を言わさぬ手際の良さで一つの夜着を着せられた。
それは夜着というより、男を視覚で悦ばせる為だけの肌が透ける衣だった。
「待って! こんなものは着られない、」
だが、侍女たちはただ「どうぞベッドの中でお待ち下さい」の一点張りで、支度を終えると、シーア唯一人を残してそそくさと部屋から出て行った。
シーアは、いつシュザックがこの緑晶の間へ来るのか気が気でなく、神経質になった小動物のように部屋の中をぐるぐる歩き回っていた。
だが、時間が経つにつれとうとう腰を落ち着けたくなり、ベッドの端に腰かけた。
その間、ずっと恐れを抱きながら待っていた。
シュザックの訪れに時間がかかればかかるほど、シーアの神経はどんどん張り詰めていく。
この状況がどういったものなのか、何を意味するのか理解出来るからこそ、シーアの躰は悲鳴を上げそうなぐらい戦いていた。
しかし、もしこんな状態のシーアを見たら、シュザックはほくそ笑み……彼女の落ち着きの無さを笑うだろう。
そう思うと、持ち前の勝ち気な性格が表に出て、シーアは顎を上げて天蓋レースの中に入った。
そして、ベッドの中央に腰を下ろし、何があろうとも徹底的に闘ってやる! という意気込みを持って、シュザックの登場を待ち受けた。
もちろん、内心の恐怖は心奥深くに閉じ込めて……。
しかし、見事シュザックの思惑に裏をかかれる事になった。
なぜなら……彼は、一度もこの部屋を訪れなかったのだから。
* * * * *
「綺麗な肌だ、それに、小ぶりだが形の良い乳房をしている……」
シーアが太陽の光を浴びて、どこか儚げな表情を浮かべながら外を眺めている姿を、シュザックは自室の窓枠に腰かけて眺めていた。
シュザックは、もちろん “緑晶の間” へは立ち入る事はしなかった。
ルーガルの女性として噂通りの美しさを持ち、男の目を惹く存在にもかかわらず、あの物怖じしないじゃじゃ馬な娘に、少し思い知らしめたかったのだ。
とは思うものの、シュザック自身昨夜は安楽な睡眠を得る事は出来なかった。
媚び諂う事もしないあの娘の事を思うと、眠るのは困難だったのだ。
押しつけられた柔らかな乳房、躰から香ってくる何とも言えぬ愛らしい香いは、既に躰が覚えている。
その相手に、あの清んだエメラルドの瞳で真正面から見つめ返されれば、どんな男でも最初の言葉は失ってしまうだろう。
相手が誰であろうとも怯まない、あの真摯な瞳はローレルの武器と言っていい。
本人がそれを知っているのかどうかは……疑問だが。
それにしても、外見と内面のギャップの差が凄いな。
シュザックは、頬を緩めてクスッと笑うと手元の書簡に視線を落とした。
“我がルーガル王国・王族より、貴国・皇太子正妃を望まれた事、有り難く思います。しかしながら、現在貴国・皇太子正妃に相応しい年齢の姫は、我が国には存在せず、またまだ幼い姫にしてみましても、既に婚約の儀が整っております。誠に残念ではありますが、今回のお話はなかった事とご理解いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
残念な結果ではありますが、この件をもって両国がさらにより近しき国になった事を心から歓迎致します。その意を表し、我が国の名産品でもある〔リュカ〕特産品をお送り致します。
ルーガル王国宰相 ダン・ヴィンセント ”
「体よく断られたって事か……。だが墓穴を掘ったな。既にギルから報告を受けているというのに。ルーガルの皇太子・ランドルフには、美しい妹姫が居ると」
書簡と共に送られてきた一つでもある、香料が入った小さな壷を取ると、蓋を開けて香りを吸い込んだ。
「……これだ!」
この香りは、ローレルの躰から放たれていたものと同じだ。
その香りを吸い込むだけで、まるで側にローレルが居るような錯覚に陥る。
「不思議だ……。我が国の香料を塗っている筈なのに、ローレルからはこの不思議な〔リュカ〕の香いが漂っていた」
その香いからして、ローレルが紛れもなくルーガルの女性だという事が立証された。
だが……
シュザックは、ローレルが既に室内に消えた事を確認すると、同じように立ち上がり、左手には書簡・右手には壷を持って執務室へと向かった。
そこには、既に起きて働いているギルの姿があった。
「おはようございます、殿下」
シュザックは手を上げて挨拶を受けると、山積している仕事の山を尻目に椅子に座った。
「今朝は、もっと遅い時間にお出ましかと……」
その嫌味に、シュザックは頬を緩めた。
「ギル、ルーガルからの書簡は既に読んだか?」
「御意」
ギルは手元の資料を本棚に直すと、シュザックの側に近付いた。
「お前の意見は?」
「……武術ではルーガル王国より勝ってる我が国とは、争いたくはない。だが、血肉を好むガリオンに、人質として姫を渡すつもりはない。といったところでしょうか?」
その率直な物言いに、シュザックは苦笑いを浮かべた。
「そういう意味合いでの書簡なら、ルーガルはガリオンに先制布告した事になる。そうなると、あの貢ぎ物の意味は?」
「……姫を渡す事は出来ないが、身分の高い者にしか使う事が出来ない最高級の〔リュカ〕製品を友好国の証として送る。つまり、他国には手に入りにくいとされる……各国が欲しがる貴重な物を渡す代わり、諦めて欲しい……という事かと。ルーガルでしか咲かないと言われている〔リュカ〕で織られた反物は、最高級と伺っております。また、門外不出とされる特殊な技法で抽出された〔リュカ〕の香料は、まるで生花の如く、」
シュザックは、ギルの言葉を止めさせる為に手を上げた。
「つまり、庶民の手には入らない高級のものという事だな」
「御意」
その言葉を受けて、シュザックは椅子から立ち上がると腕を組んで執務室の出入り口へ向かった。
「ギル、ガシュールがローレルを捕えた時、ルーガルでは何が行われていた?」
「毎年1回行われる〔リュカ聖祭〕が、宮殿で行われておりました。その年に16歳を迎える乙女なら、街娘でも宮殿に招待されるとの事。その伝統祭で正式に乙女と扱われるようになり、嫁ぐ準備を始めるのです」
ギルの言葉を頭の中で反芻しながら、シュザックは “緑晶の間” へ通じる回廊へと歩を進める。
「ルーガルに潜入中の密偵に連絡を取り、何か問題が起きていないか調べるんだ」
「御意」
どう考えてもおかしい。
ローレルの躰から漂う芳香は、今回初めて手にした香料と同じだ。
どうしてローレルが、そんな高級品を使える? どうして、極秘書簡の内容を知っている?
「特に、皇太子・ランドルフの美しい妹姫の所在を確認しろ」
「……御意のままに」
訝しげな声が後ろから響いてきたが、それもその筈。
ギルはローレルの肌の香いを知らないし、貢ぎ物として届いた香料の香いも知らないのだから。
シュザックは“緑晶の間” の前に到着すると、ノックもなしに扉を開いた。
そして、いきなり大声で笑いだした。
室内には、誰もいなかったからだ。
「やられた!」
だが、シュザックは楽しそうに笑みを浮かべた。
面白い! もし俺の推測が正しければ、とてつもない宝を手中に収めた事になる。
さて、ハーレムでどういう事になるのか、ローレルはわかっているのかな?
昨夜の既成事実は、ハーレムの女たちから “寵愛を受けた一夜” だと思われているんだぞ?
シュザックは唇の端を上げてニヤッと笑うと、意気揚々としながら自室へと引き返し始めた。
しかし、その笑みは突然凍りついた。
特に可愛がっていた女にさえ立ち入り禁止を命じていた “緑晶の間” に、何故ローレルを誘ったのか……その真意が自分でもわからなかったからだった。