Your Site Title / Tamplate#019
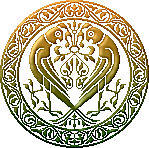
『引き寄せられた、出会い』【1】
「さぁ、香油を塗りましょう」
籐で作られたベッドに、シーアは裸体で腹這いになっていた。
昼過ぎに、ガリオン帝国首都バーンに到着した後、ある場所へ連れて行かれたのだ。
ガリオン帝国貴族御用達の市に出される乙女たちの……身を清める場。
シーアも、その内の一人となって侍女たちに躰を磨きあげられていた。
冷水で身を清められた後、熱い浴槽に入り、躰の汚れを擦られ…再び熱い湯へ。
またも冷水で肌を引き締めると、そのまま花びらを入れた浴槽に入り、香油で全身マッサージを受けた後、再び熱い浴槽から冷水へと移り、肌を引き締める。
その間にも、髪も洗われていた。
そんな理由から、シーアは疲れはてて……もうぐったりと籐のベッドに横たわっていたのだ。
確かに香油を塗られるのは気持ちがいい。だけど、ヴィンセントの家では……こんな風にされた事はなかった。
わかってる……。この躰を売る為にしっかり磨き上げて、値段を吊り上げようっていう事なのよ。
シーアは疲れ切った目を開けて、空ろなまま周囲にいる乙女たちを観察した。
彼女たちは、様々な人種の集まりだった。
透けるような白い肌の持ち主もいれば、輝くような黒い肌の女性、黒い髪を持つ女性に、わたしと同じ蜂蜜色の髪を持つ女性も……。
人種は全く異なってはいるが、皆それぞれに美しく豊満な躰を持っていた。
そんな彼女たちは、何も恐れてるようには見えなかった。
――― これから起こるであろう出来事を。
前だけをしっかり見つめ、誰よりもいい場所で働きたいと願ってるようにさえ見えた。
何て事なの! どこの場所で働いても、同じ事だってわからないの? 結局は、この身が売られるっていう事なのよ? 好きでもない人に、我が身を捧げるという事なのに……何故そんなに目を輝かせていられるの?
彼女たちの気持ちが全くわからない、理解出来ない……。
シーアは内から震え出す恐怖を追い払うように、頭を降り続けた。
薄衣をかけられると、部屋を移動させられた。
長椅子に座らされ、リラックスするような体勢を取る。
すると、一人の30代ぐらいの女性が近寄ってきた。
「まぁ、何て綺麗なお嬢さんだこと! わたしが、今まで結ってきたどの女性より、とっても美しいわ。あなたなら、きっと善い所で買って下さいますよ」
善い所? ……そんなの何処だって一緒だわ。
彼女はシーアの真意を知る事もなく、髪を徐々に結い上げていく。
「それに、綺麗な髪をしていますね。よくここまで、髪を見事に扱ってきましたわ。貴族の方たちでも、ここまで見事にお手入れをされてる方々は少ないですよ。……殿方というものは、こういう髪に顔を埋めたいと思ってるんです。だから、あなたは、」
「……って」
「えっ? 何か仰しゃいましたか?」
「それなら、こんな髪切ってと言ってるの!」
シーアは、吐き捨てるように言葉を投げつけた。
そして、自分の苛立ちをこの女性に向けてしまった事に、腹を立てた。
わたしったら、何を言ってるの?
この女性にやつあたりしてもどうしようもない事だって……わかってるのに。
「……お嬢さんは、好んで売られるわけではないんですね?」
「好んで売られたいだなんて、そんな風に思う人は絶対いないわ」
髪に触れていた手がピクッと止まるが、再び動きだした。
「それは、一概には言えませんよ。若さを武器にして、お金を稼ぎ……いい暮らしがしたいと望む者もいれば、どなたか有力者の愛人になって、生涯贅沢をしたいという方もいますからね」
「そんなの……そんなの嘘よ」
シーアは、混乱する気持ちを断ち切るように拳を作った。
贅沢が何だと言うの? 贅沢で幸せは買えない……買えないって事をわたしは知っている。
「いいえ、嘘ではありませんよ。わたしはあらゆる乙女たちを見てきました。貧しい故売られる乙女もいましたが、だいたいは神から受け継いだ美貌を武器にし、有力者の目に留まりたいという乙女が多かったですわ」
「でも…わたしはそうじゃない」
その髪結い女性は気を悪くしたのか、口を噤むとどんどん髪を結っていく。
しばらくすると、その女性が口を開いた。
「こうなったからには、舞台上では美しく・気品があるように振る舞いなさい。そうすれば、あなたならきっと貴族御用達の娼館の中でも最上級の館に買われるでしょう。今日は何方がいらっしゃってるのかは知りませんが、もしかしたら、有力者のハーレムに買われるのも夢ではありませんよ。ただ、舞台上では決して口答えをしてはいけません。いくらあなたのように美しい女性でも……逆らったりすれば、買って下さる方は一番下位の娼館になってしまう事もありますから」
シーアはやっと目を開けて、鏡越しにその女性の顔を見た。
彼女が、安泰に暮らせるように助言をしてくれたからだ。
わたしが、ひどい言葉を投げつけたのに。
途端、その女性の目が大きく開かれる。
「まぁ! 何て、見事な目の色をしてるのかしら。まるで、エメラルドだわ。あなた……もしかしたら、もっといい所へ売られるかもしれないわ」
シーアは哀しそうに微笑んだ。
「売られるのなら、何処でも同じだと思うわ。でもあなたの助言には感謝してる。ありがとう。……それに、あなたの腕は凄いわ」
見事に結い上げられた髪を見た。
顔の輪郭がはっきり見え、いつもより美しく見える。
自嘲するように、シーアは口角を上げた。
美しくなんて……見えなくてもいいのに。そうすれば、わたしはココにいる事はなかった筈だもの。売られる為に……わざわざ捕われる事もなかったんだから。
「それでは、善き相手と巡り会えますよう……」
彼女が去って行こうとした。
「待って!」
シーアは、唐突に呼び止めてしまった。
なぜなら、この女性ともう少し話がしたかったからだ。だが、何を話せばいいのかわからず目を泳がせた。
「……あなた、お名前は?」
シーアは、考える間もなく…いつしかそう尋ねていた。
名前を聞かれたのが嬉しかったのか、髪結いの彼女は微笑んだ。
「シャノン・リーと申します。……お嬢、さまは?」
まさか、逆に聞かれるとは思ってなかった。
シーアは一瞬躊躇した。
唇を噛み、視線を一度伏せる。
どうする? 彼女、 シャノン・リーはとってもいい人だわ。
感情的になったのに、それでも良いとされる行動を教えてくれた。
普通なら、わたしの態度に怒ってしまって、助言はしてやらない……と思っても不思議ではないのに。
シーアは視線を上げて、真っ直ぐ彼女を見た。
シャノン・リーの瞳は、茶色の穏やかな清んだ目をしてる。
彼女になら……
「わたし、シーア……シーアローレルというの」
シャノン・リーは優しく微笑んだ。
「お嬢さまに、とっても似合った素敵な名前ですね」
そう言うと会釈し、次の乙女の髪結いをする為、去って行った。
その立ち去さる後ろ姿を見て、何故か胸が苦しくなった。
皆がどんどん去って行くという…焦燥感だろうか?
シーアは、思わず独り言を呟いた。
「一人ぐらい、わたしの名前を知ってる人がいて欲しかったの……まだ乙女のままの……ルーガルのシーアローレルがここにいたんだって」
シーアの悲嘆した瞳から、涙が一粒だけ零れ落ちた。