Your Site Title / Tamplate#019
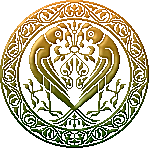
『既成事実、寵愛の一夜』【2】
シュザックが “緑晶の間” に来た……とは露知らず、シーアは侍女が慌てて静止させるのも振り払って、ハーレムへの道を急ぐように歩いていた。
「お待ちくださいませ! ホークさまのご命令がない限り、この宮から出る事は許されておりません」
「彼は、もうわたしに用はないはずよ。一晩わたしを拘束したのだから。……逃げるんじゃないわ、ハーレムへ戻るのよ!」
シーアの言葉に、侍女がほんのり頬を染めて俯いたが、それに気付く事なくシーアは前だけを向いて歩を進めた。
決して触れて止めようとしないのをいい事に、シーアは回廊から階段へ差しかかると、そのまま駆け降りた。
ハーレムとシュザック皇子の宮殿を扉一枚で隔てている空間に出ると、そのまま常勤しているであろう衛兵に向かって口を開いた。
「その扉を開けなさい!」
衛兵は何事かと一瞬目を白黒させてシーアを見たが、その後冷静に慌てているる侍女へと視線を移し、再びシーアを見つめた。
「申し訳ありません。殿下より直属の命がない限り、この扉を開けるわけには、」
まるで貴族のように……優雅に頭を垂れると、彼の後ろで一つ纏めにした長くて黒い髪がさらさらと肩から胸へと流れ落ちた。
その艶やかなストレートヘアに目を惹かれたが、シーアは意識を元に戻すと衛兵を直視した。
「開けなさい!」
「どうか、無理を仰しゃらないで下さい」
衛兵は、断固とした面持ちで扉を守っていた。
侍女はこの成り行きにどうすればいいのかわからず、ただその場でおろおろしている。
それを目の端で捉えながら、シーアは作戦を変えた。
にっこり微笑んで衛兵の側へ近寄ったのだ。
「あ、あの!」
シーアの突然の変化に、目の前の衛兵は驚愕したように目を見開いた。
彼の逞しい胸板は激しく上下している……、そのような姿はルーガルで何度も経験してきた。
相手は皇太子・ランドルフ王子の他に、隠れて恋の駆け引きを試みようとした者たち。
シーアが無邪気な仕草をすると、次兄のローガンは頬骨の辺りを染めながらよく叱咤したものだ。
男をからかうものではないと。シーアは王子の未来の正妃として認められているから何も起きないが、一歩間違えば男は自制心を失い獣になるぞと、何度も言い聞かせるように言った。
でもローガン兄様……、時には役に立つ事もあるわ。
侍女に話の内容が聞こえないよう、衛兵に身を寄せて胸を逸らし、上目遣いに彼を見上げた。
「あなたならどちらがいい? シュザック皇子の……ハーレムに囲われたわたしに、あなたが突然襲ってきた……と言うのと、ハーレムの女が部屋に戻りたいから扉を開けた……と言うのと。後者なら、わたしはシュザック皇子に、あなたをお咎めにならないでと進言してもいいわ」
しかし、シーアの言葉に衛兵は口元を引き締めて、目を細めた。
「俺は……この扉を守る身! 開ける事は忠義に反します。それに、殿下は決してお……わ、私が殿下の女性に手を触れる事はないと、重々承知しておられます」
なんて、忠義心なの。……それほどシュザック皇子を信頼しているという事?
シーアは、そっと彼の腕に触れた。
「ローレル様!」
後方に控えていた侍女が、シーアの態度に驚きを隠せず声を荒立てた。
だが、シーアは侍女の言葉に耳を傾ける事はせず、衛兵の目だけを覗き込むようにジッとしていた。
後ろで、バタバタと走り去る音を聞きながら、もっと彼に近寄った。
「……えぇ、あなたはそんな事はしないわ。でも、わたしがそうさせたとしたらどうかしら? 確かに、あなたはわたしに触れる事は許されないのでしょう。でもわたしが導いて触れさせたら? シュザック皇子は……」
端から見れば艶めかしいかもしれないが、シーアは少し顔を伏せて自嘲するようなため息をついた。
自分の考えは、見当違いも甚だしい。
だが、シュザック皇子がわたしを寵愛していると見せかけたら……多少は物事が変わってくる。
シーアは、衛兵の手首まで撫で下ろし、汗ばんだ掌に指で触れた。
こんな時に、乙女の儀式に立ち向かう前に習った<愛技法>が役に立つなんて。
心の中で荒れ狂う気持ちを抑えながら、教えられたツボを触れるか触れないかの感覚で円を描く。
だんだん、衛兵の息遣いが荒くなってきたのがわかった。
「何て……言うかしら? わたし自身にも怒りは及ぶかも知れないけれど、あなたを見る度、シュザック皇子は嫌になるかもしれない。唯一皇子だけが触れる事が出来るハーレムの女に、他の男が触れたと思ったら?」
「で、殿下は決してそのような事は!」
まだ忠誠心が揺らがない。どうして?
「そう……、どっちにしろ開けてくれないのなら一緒よね」
「はぁ?」
シーアは、仁王立ちしている衛兵の両足の間に、片足をそっと入れて下半身が軽く密着するようにすると、手を上へと伸ばした。
「試してみましょう。シュザック皇子が……あなたを罷免するのかどうか」
衛兵の項に触れると、そっと背伸びをした。
キスをするつもりは全くなかったが、こちらもこの話が真実だと信用させる必要があった。
「ご無礼をお許しを!」
乳房が衛兵の強靭な胸板に擦れた瞬間、衛兵はシーアの腕を掴むと勢い良く引き離した。
「……ハーレムへ戻る為の、扉を開けましょう」
鍵穴に鍵を入れて回すと、他の衛兵に指示を出して扉を開けさせた。
シーアは安堵のため息を漏らさずにはいられなかった。
「ありがとう。もしシュザック皇子と……話す事があれば、あなたの事を手放しで褒めておくから」
逃げるように衛兵の横を通り抜けた。
シーアが一歩ハーレムの敷地へ入ると、専用の侍女が急いで走ってきた。
だが、シーアは青ざめた顔で、真っ直ぐ前を向いて歩いた。
シュザック皇子の宮殿から逃げたかったとはいえ、自分から男性に身を寄せた事実を、今さらながら実感したからだ。
何故、何とも思わずあんな振る舞いが出来たのか、今ならわかるわ。
それは、ルーガルに居た時と全く同じだったから。
ローガン兄様は、わたしが “水晶球の祈り” に守られているからと言ってたけど、それはまた違う。
そういう行動を取っていたのは相手の方で、わたしではない。
わたしは、愛を囁く彼らを何とも思っていなかったから、あんな事が出来たのだ。それは先程の衛兵にも言える事。
衛兵が屈強逞しい男性であっても、わたしにとってはルーガルでの出来事と全く同じだった為、すんなり行動に移せた。
もし、これが……あのシュザック皇子なら。
皇子の面影や引き締まった躰・まるで愛撫するかのような声を思い出しただけで、シーアの躰は異常を示した。
心臓が激しく高鳴り、躰がカァ〜ッと燃え出す。
突然のその反応に、シーアの躰から一気に力が抜け落ちた。
結果、ふらつきながらその場に膝を折る羽目に陥った。
「ローレルさま!」
侍女がシーアを支えるように腕を取るが、シーアは石畳をジッと見下ろした。
いったい何が違うというの? ランドルフ王子とシュザック皇子。
まるで白王子と黒皇子に例えられるような外見を持つ二人は、魅力的な男性だと思う。
王族という称号を除外視しても、独特の雰囲気を持つ彼らには目を惹くものがあるだろう。
それなら、どうしてもわたしはランドルフ王子に対して何も感じなかった?
キスをされ、愛撫され、魅力溢れる女として扱いを受けたにもかかわらず、どうしてランドルフ王子の未来の正妃という立場から逃れようとしていたの?
シュザック皇子は……あの日、肌を晒したわたしを視線で射貫いただけで……戸惑わせた。
そして、あのキス。あれは、わたしが一度も観たことのない世界を垣間見せた。
もう一度……その世界を覗いてみたいと思わせるような……その行為は、とても巧みだった。
つまり、二人の経験の差という事?
「ローレルさま?」
「……だ、大丈夫」
シーアがゆっくり立ち上がると、侍女が衣装についた砂を払った。
シーアは無言で回廊を歩き出したが、そこには既に支度を整えたハーレムの女性たちがシーアの行動をずっと眺めていた。
息を呑んだように表情を強ばらせ、皆口を閉ざしていた。
その異様な空気にやっと気付いたシーアは、周囲に視線を向けた。
何? ……こんな風に、誰もがわたしを見つめてくるなんて。しかも血の気を失ったように、顔を白くさせてる。
「ふっ」
シーアは、口元を緩めて笑った。
きっと、それはわたしも同じだわ。何か、とんでもない事実を思い知らされたような感覚に陥り、茫然自失となったのだから。
シーアはその思いを突き止めるのは後にすると、自室へと向かって歩き出した。
シーアは気付いていなかった。
ハーレムの女性たちがシーアを注目しているというのに、口元を緩めて微笑んだり、胸を張って堂々とした仕草で自室に戻る行為が、いかに愚かで無謀なのかという事を。
シーアは魅力的で、人目を惹きつける美しい女性かも知れないが、実際は成熟した女性ではなかった。
躰は大人の女性でも、心の中はまだ少女でしかなかったのだ。
男女間の関係など机上の空論でしかなく、既にシュザック皇子から寵をいただいているハーレムの女性たちの燃えるような嫉妬心など、全く知るよしもなかった。